
 現在、びん沼は流れもほとんどなく、すっかり「沼」となっています。
現在、びん沼は流れもほとんどなく、すっかり「沼」となっています。びん沼に生える植物も、湿った場所を好む種類が多く自生しています。
写真の左側の草は、「ヒシ」です。
実がちょうどひし形になっていて、食べることができるそうです。
(試したことはありませんが。。。。)
右側の草は、「マコモ」です。
写真のように、少しくらい水が深いところでも生えることができます。
●さいたま市・川越市・富士見市 びん沼●
 埼玉県南部、とりわけさいたま市や川越市は近年人口が増加し、
埼玉県南部、とりわけさいたま市や川越市は近年人口が増加し、
 現在、びん沼は流れもほとんどなく、すっかり「沼」となっています。
現在、びん沼は流れもほとんどなく、すっかり「沼」となっています。
びん沼に生える植物も、湿った場所を好む種類が多く自生しています。
写真の左側の草は、「ヒシ」です。
実がちょうどひし形になっていて、食べることができるそうです。
(試したことはありませんが。。。。)
右側の草は、「マコモ」です。
写真のように、少しくらい水が深いところでも生えることができます。
 びん沼のそばには、休耕田がいくつかあります。
びん沼のそばには、休耕田がいくつかあります。 アザミのお花畑のそばには、白い野いばらの花がたくさん咲いていました。
アザミのお花畑のそばには、白い野いばらの花がたくさん咲いていました。
野いばらは、よくお花屋さんで売っているバラの仲間です。
しかし、美しいものにはとげがある、との言葉があるように、
野いばらにもとげがありますのでご注意を。



沼のほとりは、結構湿っぽくて、
そこに生える植物もそのような環境に適応しています。
写真の木はアカメヤナギというヤナギの木です。
有名なシダレヤナギとちがうところは、葉っぱが細長くないこと、
その名の通り若い葉っぱが赤みをおびていること、葉っぱのうらが白っぽくなっていることです。
 この他、沼のまわりでは、茎にも細長い葉っぱのついている「ヌルデ」という木が生えていました。
この他、沼のまわりでは、茎にも細長い葉っぱのついている「ヌルデ」という木が生えていました。
地味な木ではありますが、紅葉のころは味わい深いものがあります。
そのほか、ニセアカシアの林が沼の北側にあって、
ちょうど私が訪れたころは一面に白い藤のような花をたくさん咲かせていました。
(ニセアカシアも藤もマメ科の木なので、兄弟のような関係なのです)
今回は植物にスポットを当てましたが、びん沼は絶好の釣りスポットとなっていて、
私が訪れた日も平日にもかかわらず多くの人が釣りを楽しんでいました。
魚にとってもびん沼はいい環境なのでしょう。(釣り人がいる、という意味では受難なのかもしれませんが。。。。)
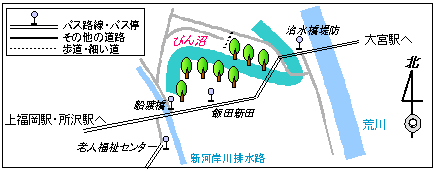

・「にわぜきしょう」・
帰化植物ですが、現在では野生化。
今では水のある風景にとけこんでいます。
このページは 1999年5月12日に取材しました。